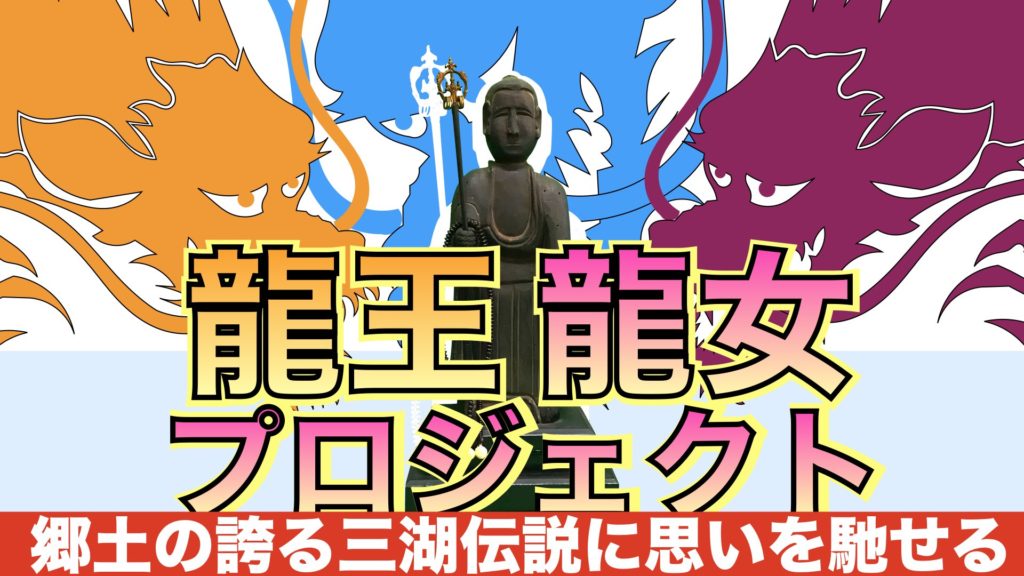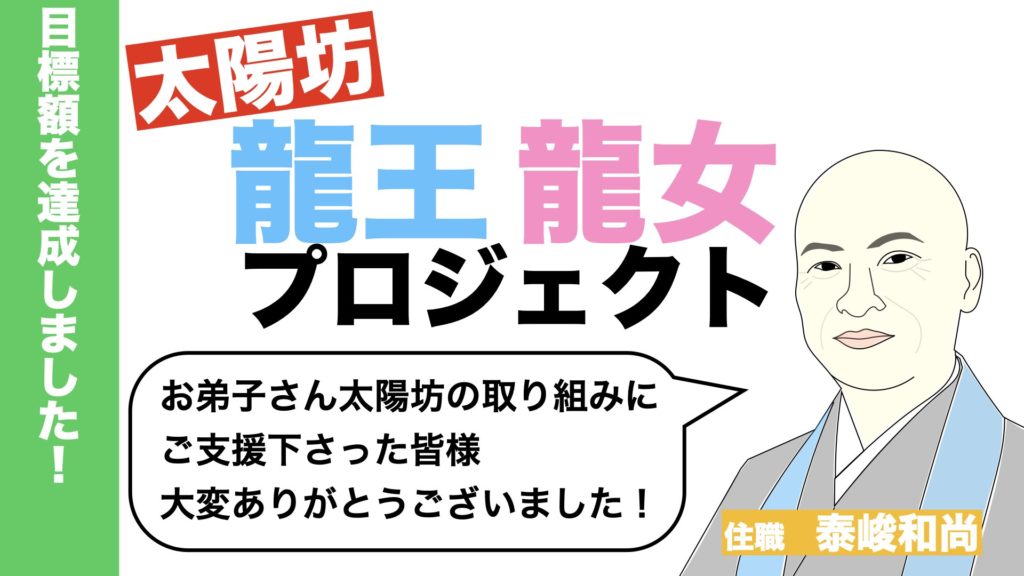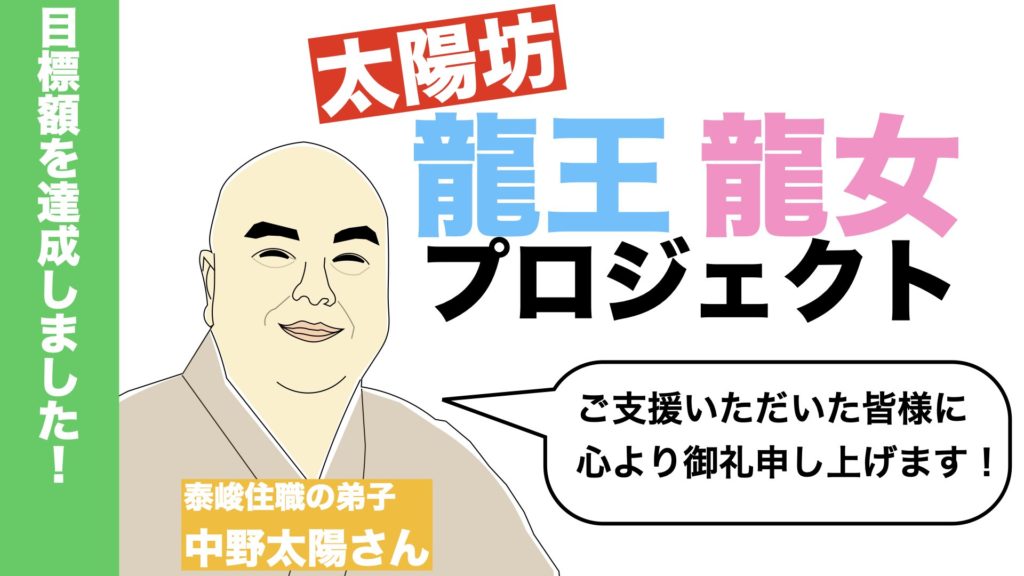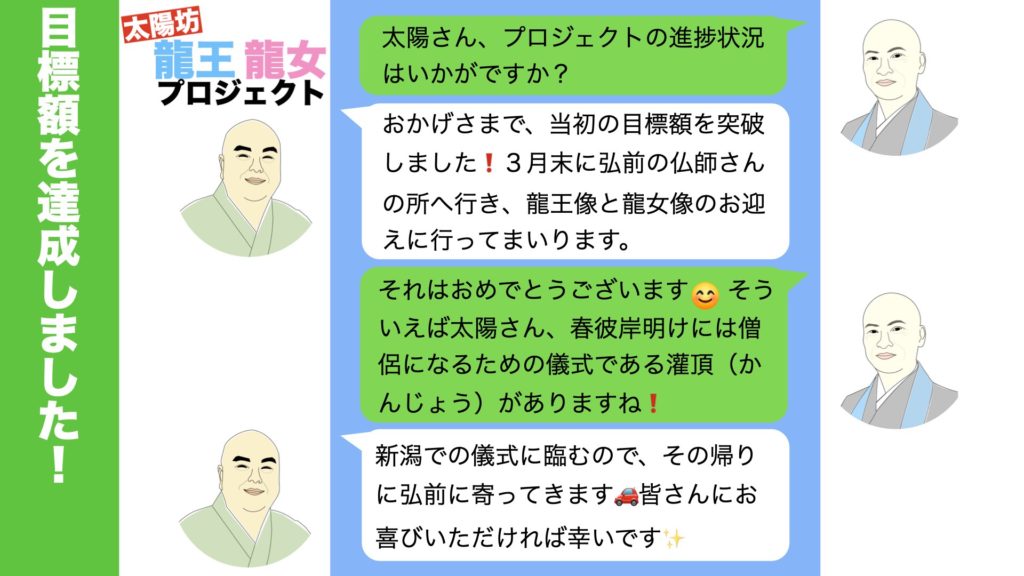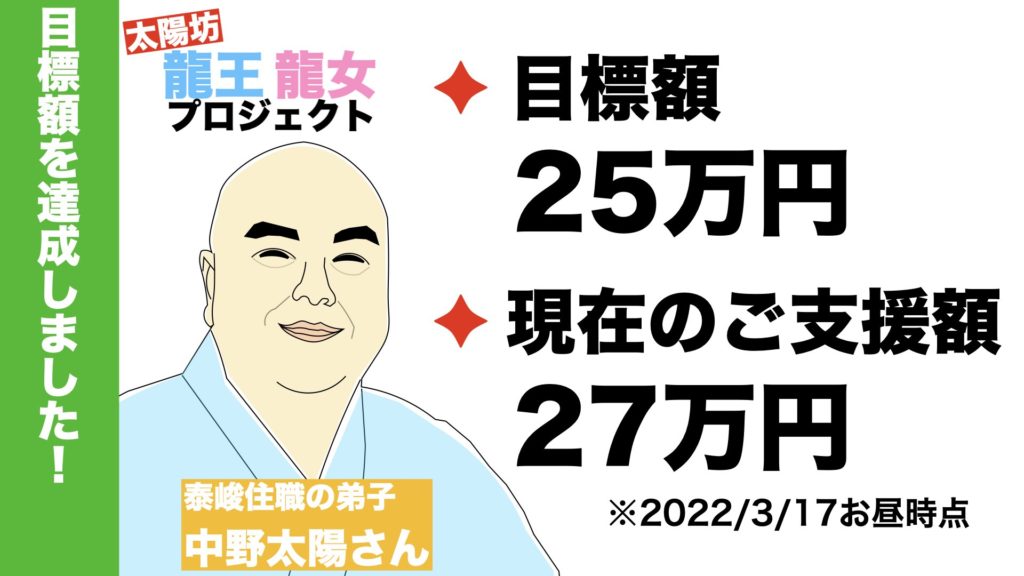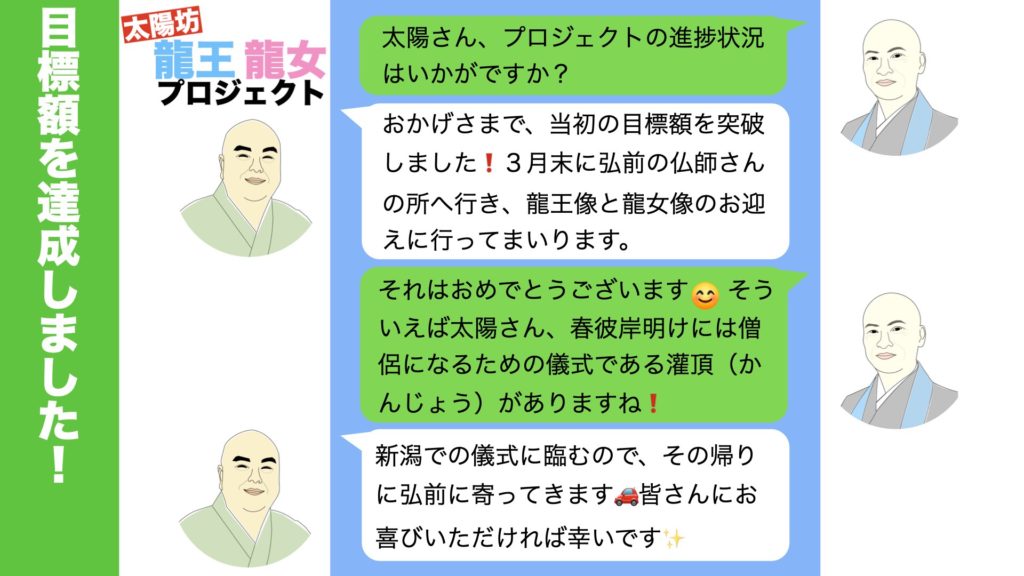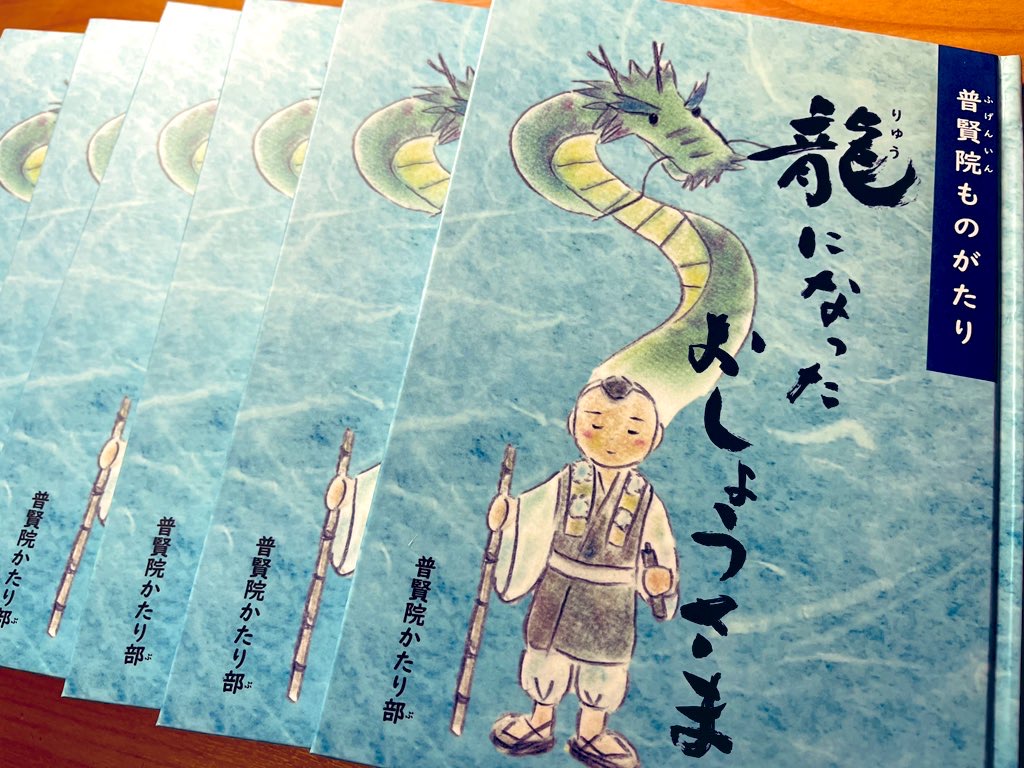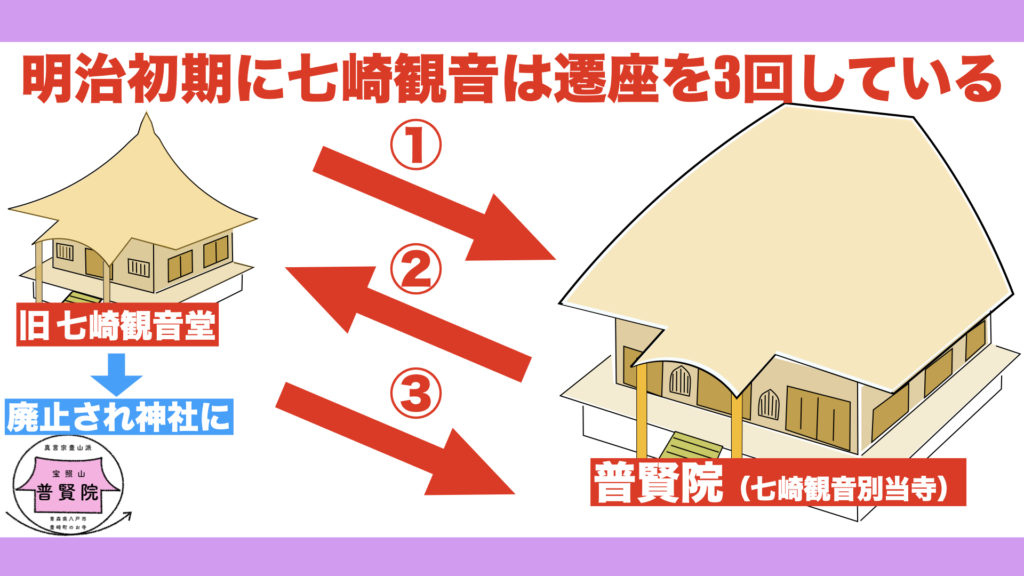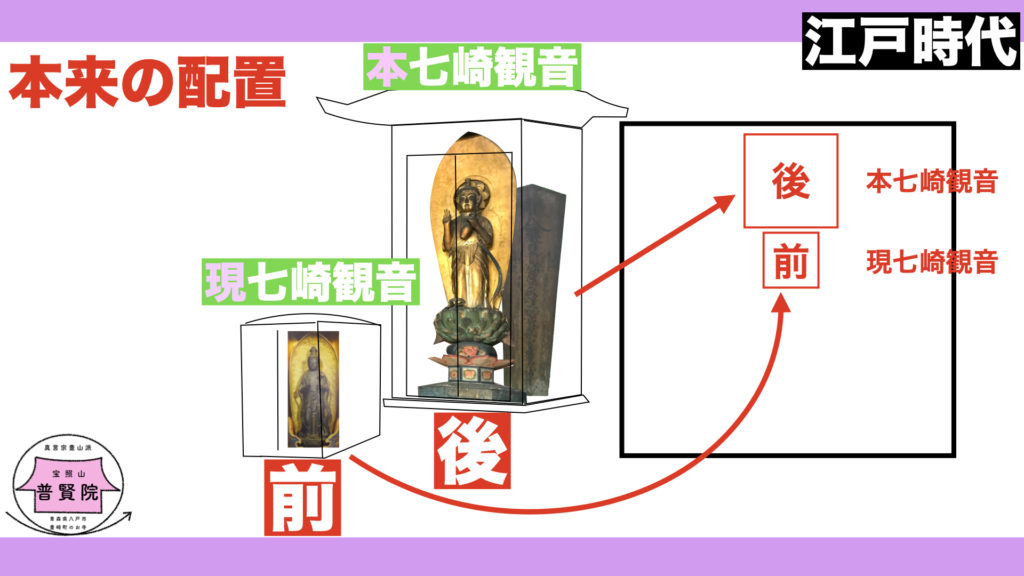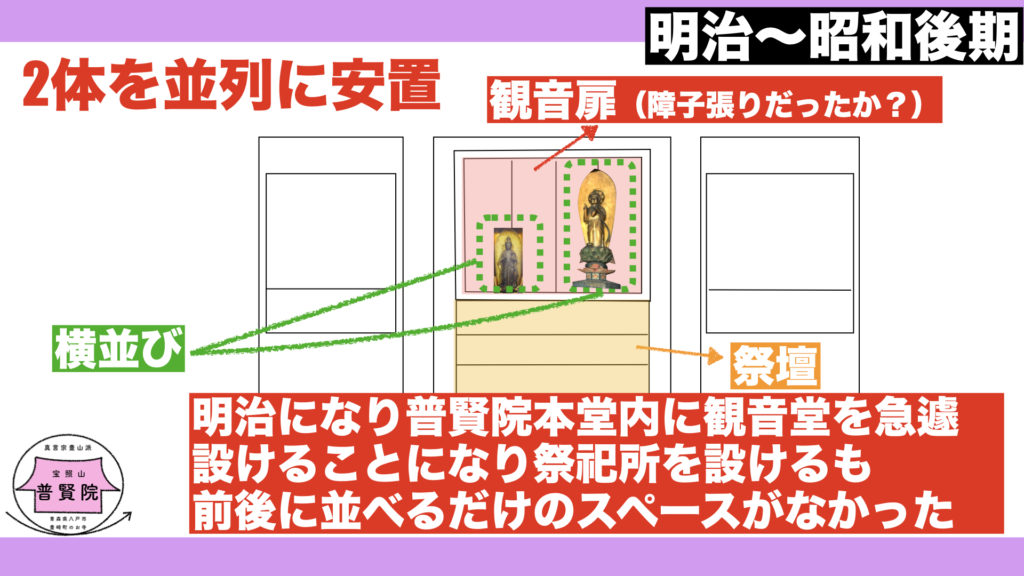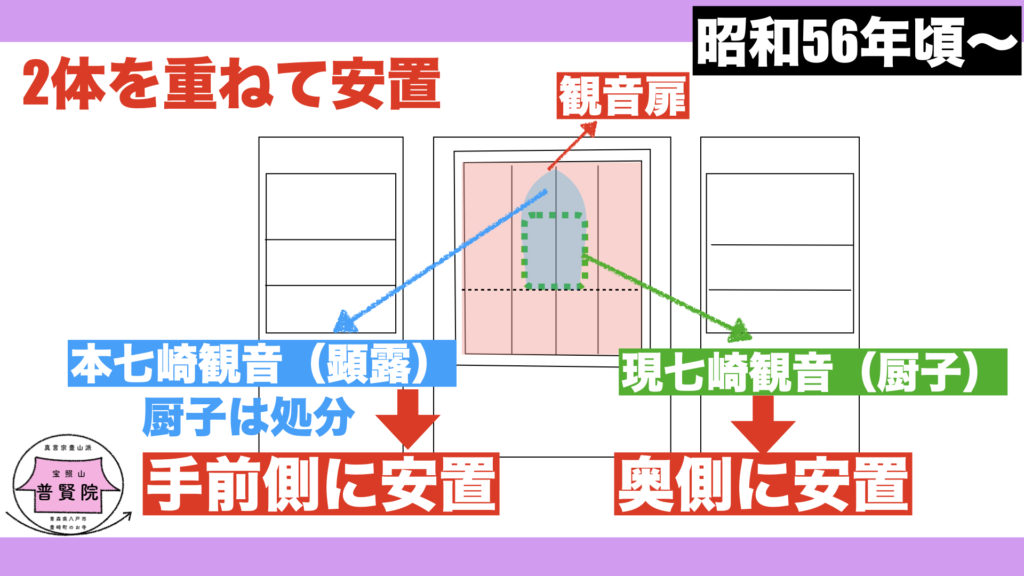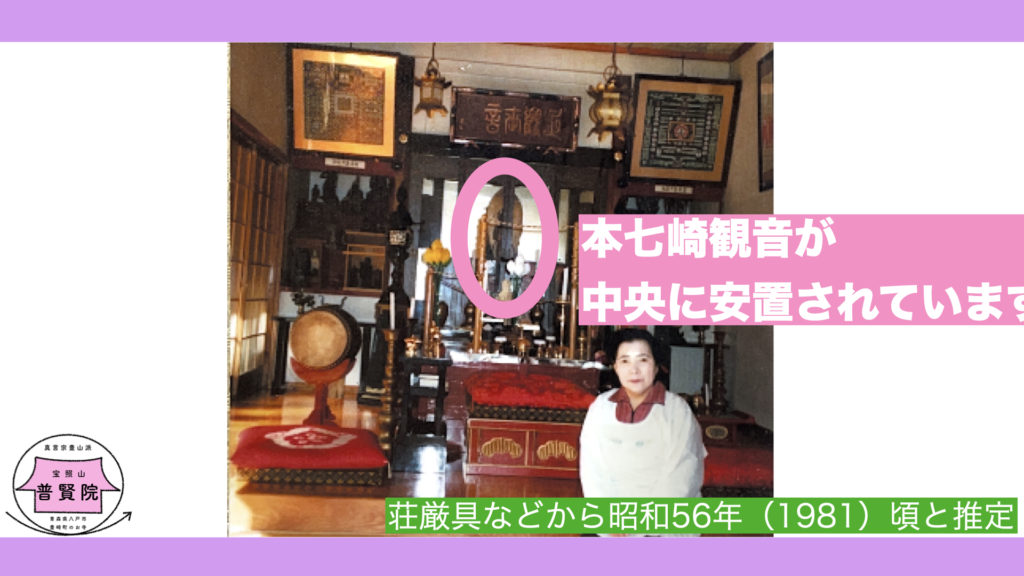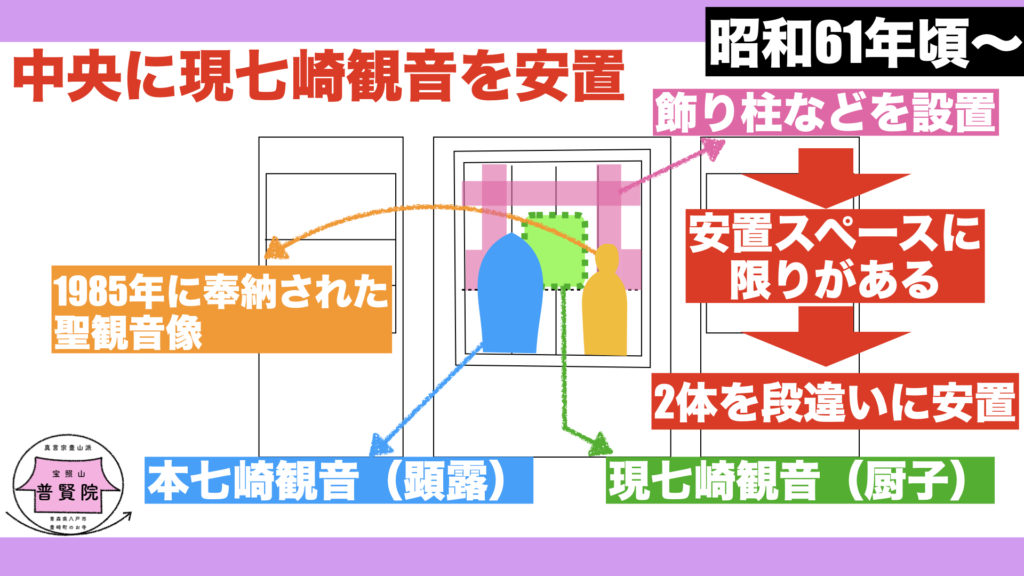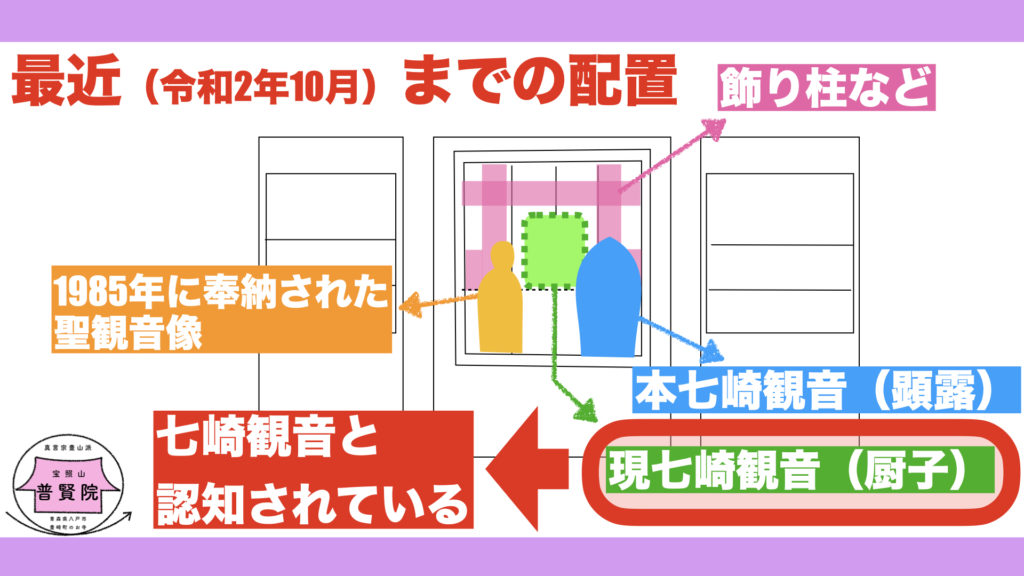拙僧泰峻の弟子である
太陽坊こと中野太陽さんの発願が結ばれ
今春当山に
龍王像と龍女像が
新たに奉納されることになりました。
お納めいただく龍王像と龍女像は
当山に祀られる
南祖法師(なんそほっし)尊像の
脇侍(わきじ)としてお祀りされます。
本年秋に完成する新本堂では
観音堂の脇堂に
南祖法師を中心にお祀りする
南祖堂というお堂を設けられます。
太陽さんの浄行により
十和田湖伝説のみならず
八郎潟と田沢湖にて語られるものを含む
三湖伝説へ思いを馳せられる場所が
当山に用意されることは
とてもありがたいことと感じます。