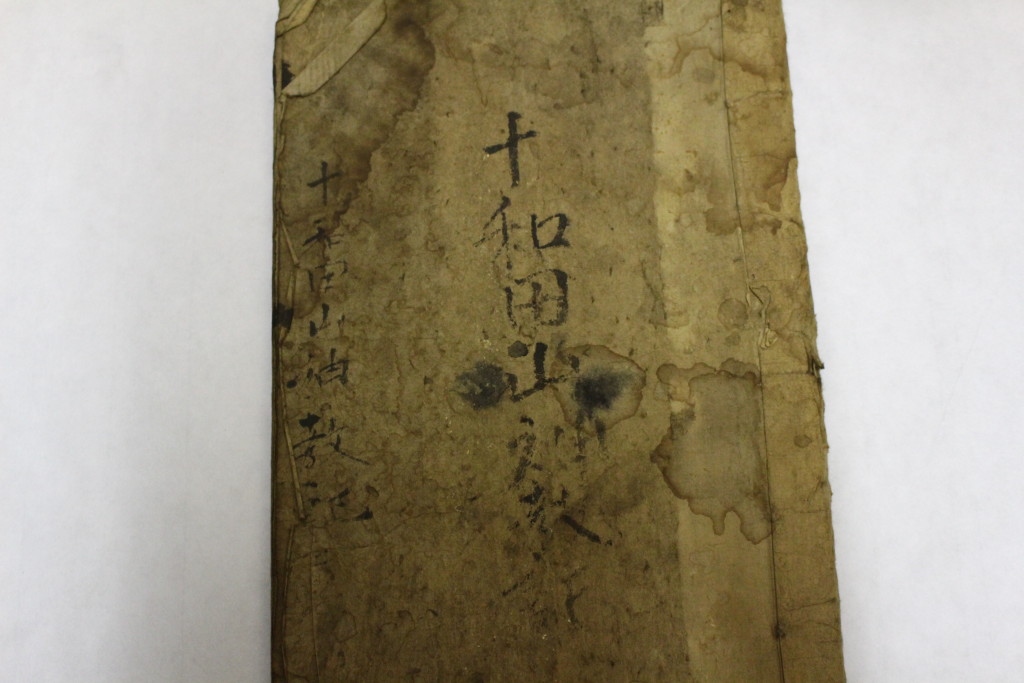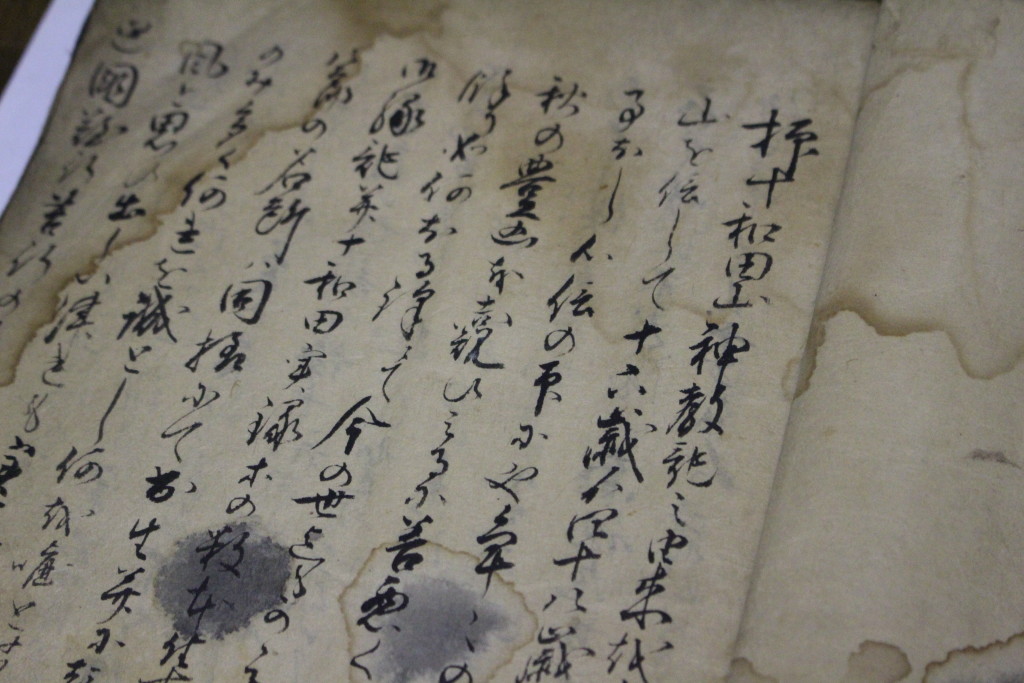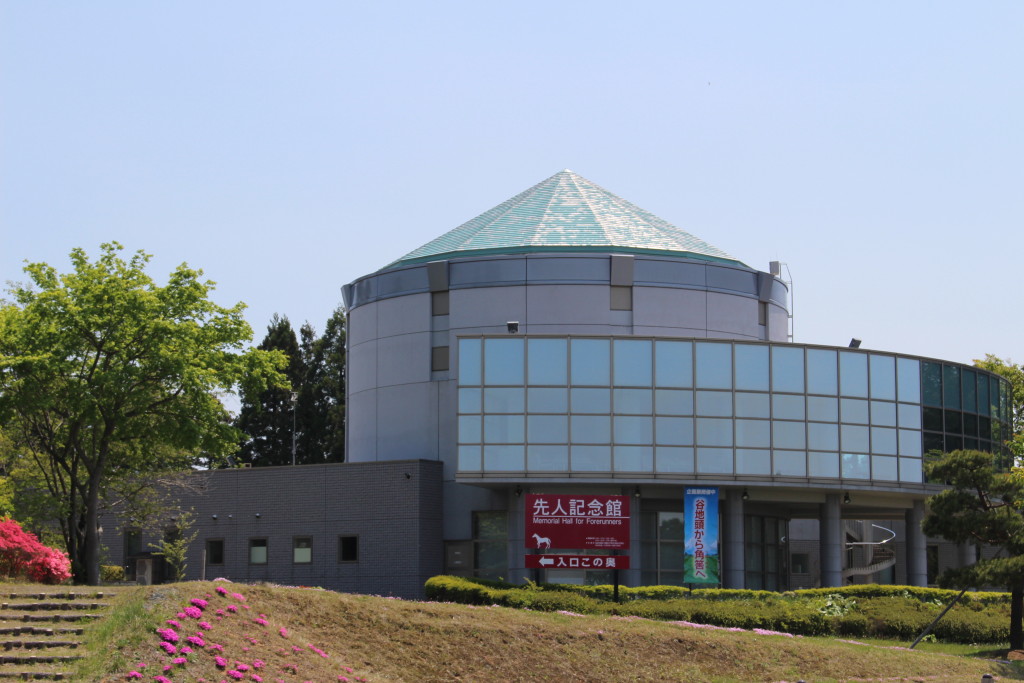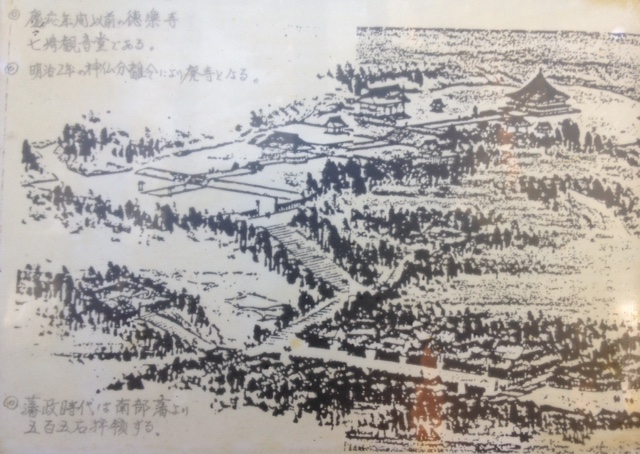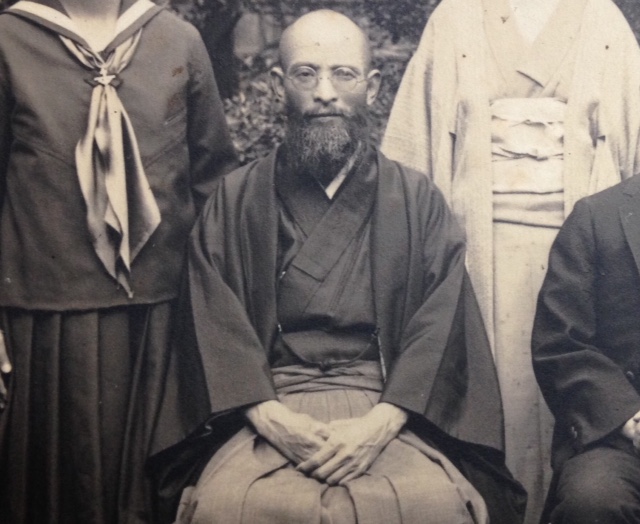青森県の
景勝地のひとつ
十和田湖。
十和田湖には
伝説が伝えられます。
十和田湖伝説に登場する
南祖坊(なんそのぼう)は
幼少期に当山にて
修行されたとされます。
南祖坊は
青龍大権現(せいりゅうだいごんげん)
という名の神仏として
十和田神社の奥の院に
お祀りされております。
当山はかつて
永福寺(えいふくじ)というお寺でした。
南部氏が拠点を盛岡に移す際
永福寺も盛岡に改められました。
永福寺は現在も盛岡にございます。
永福寺にも南祖坊の碑が建立されております。
石碑正面に
「十和田山青龍大権現」
と刻まれております。
両側面には
「十和田山南祖坊大菩薩」
「十和田山観世音菩薩」
と刻まれております。



▼十和田神社について
http://towadako.or.jp/rekishi-densetsu/towada-jinja/
▼十和田湖伝説について(紙芝居動画)
http://towadako.or.jp/rekishi-densetsu/towadako-densetsu/