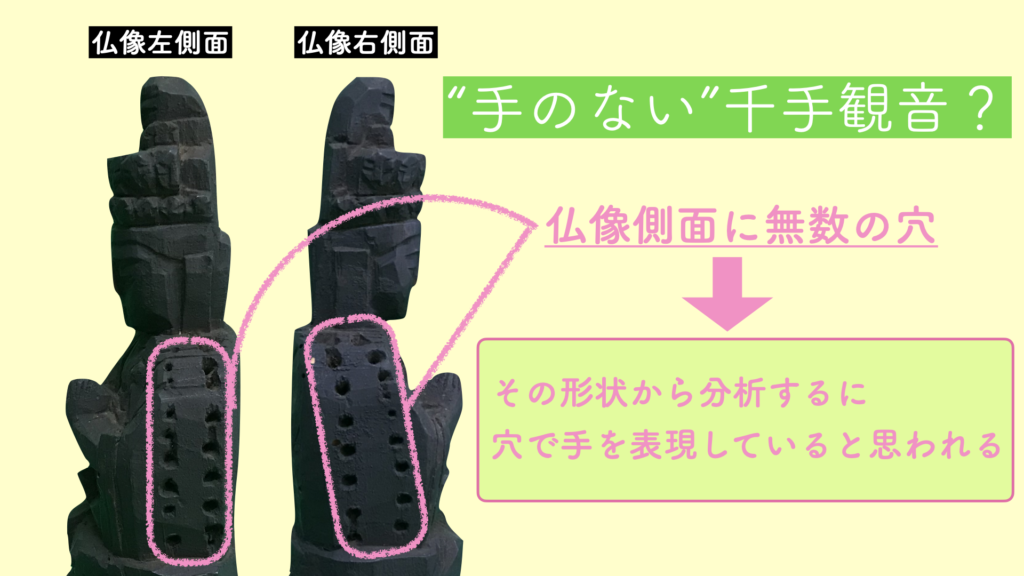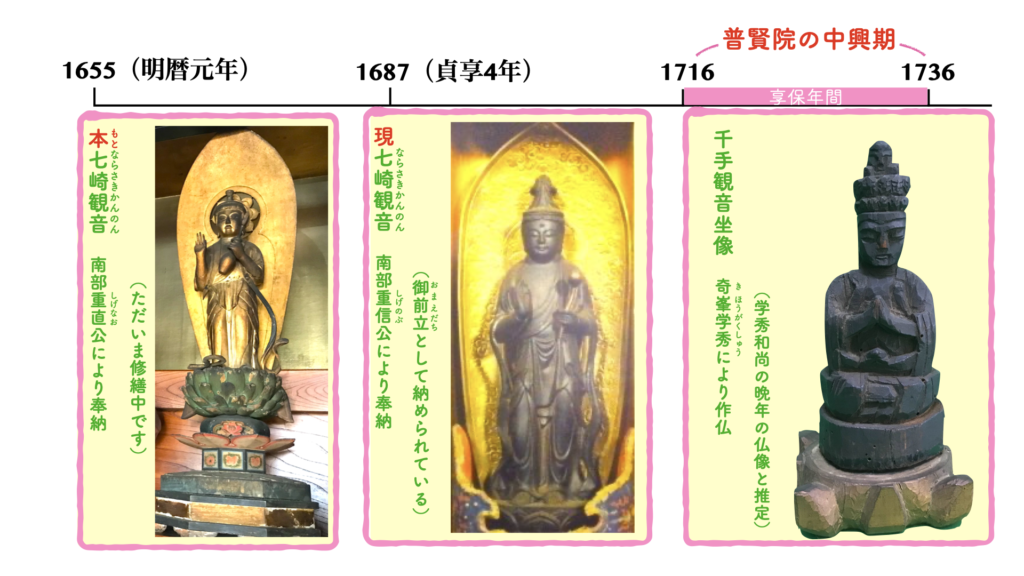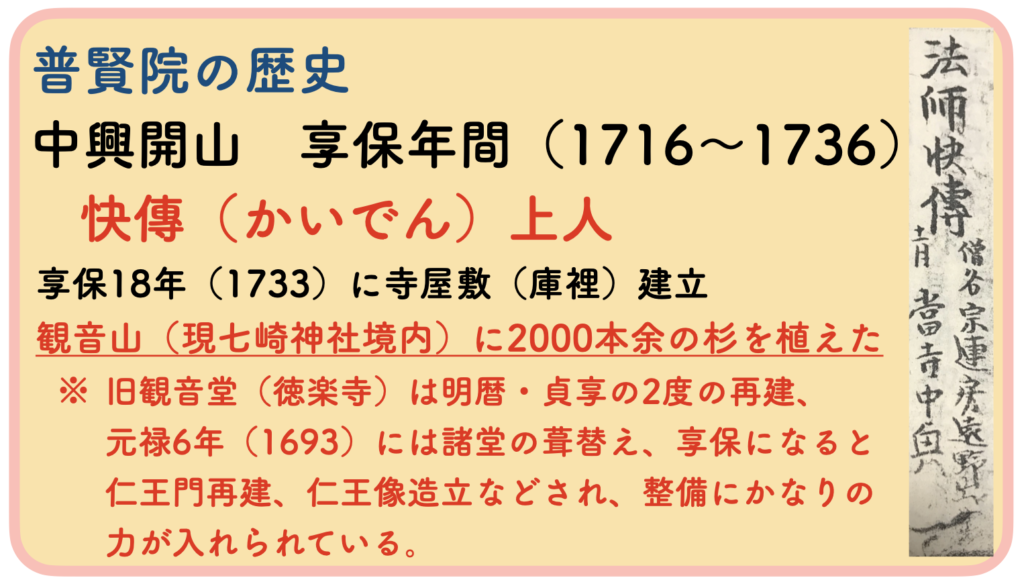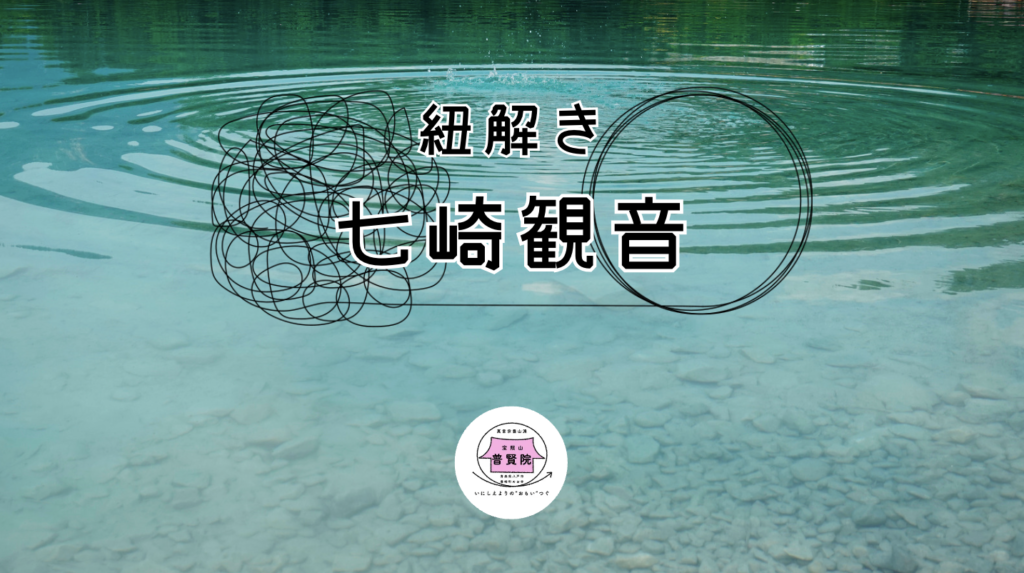さまざまな尊格について語り
お寺について語り
お寺の本尊の霊験や
巡礼や修行などの功徳など
アラカルトなものを
広く巧みに語った方々が
全国各地に存在しました。
時代により
その様相は異なりますが
仏教伝来以前にもまた
巫術に通じる方が
“聖なる言葉”を
述べていたらしいことが
古い史料は伝えています。
七崎観音についてもまた
「語り」を担った方が
いたということを
今回のテーマとして
述べてみたいと思います。
高野聖
念仏聖
勧進聖
修験者
行者
山伏
などといった言葉は
誰もが聞いたことがあると思います。
当地における資料を管見すると
山伏や修験者といった言葉が
好んで用いられているものの
無警戒かつ広義的に
使用されているような感が
あるように思います。
このことは
真言宗や天台宗といった
用語についても同様で
専門的な観点からすると
違和感ある宗派感覚で以て
片付けられてしまっている
印象があります。
現在でいうところの宗派は
実はかなり現代的なものであり
江戸期であっても
表の法流(行政上のもの)と
実際の中心的な法流が
異っているという場合もあるのです。
横のつながりや交流も盛んゆえ
諸宗諸派の交流を通じた研鑽・修行は
珍しくないわけで
在地の山伏や行者や聖といった方は
もっと習合的様相があったということが
出来るので
どのような意味を託して
用語を用いているのかについて
定義するなり含みを持たせる
一手間が必要だと思います。
僧侶と一言でいっても
正式な得度ではない形で
沙門となった私度僧という
あり方もありますし
私度僧を修験者や山伏に
含めて表現することもありますし
歴史があってバリエーションもある
用語の使用というものは
とてもデリケートなことだと感じます。
七崎観音ほか
当山には十和田湖南祖坊伝説など
いくつか語り継がれるものがありますが
それら諸縁起・伝承・伝説を
受容する社会側からの検討が大部分で
それを主導した仏教者側の
思想的背景や意図などに
焦点を当てた検討は
ほとんど見られません。
これは当シリーズでも
何度か触れている点ですが
日本的な仏教的文脈にて語られ
共有されてきたと思われるものゆえ
仏教学的アプローチは
とても有効的であると確信します。
そういう課題意識を
抱いていることを
明言させていただいたうえで
本シリーズでは先に触れた
諸聖や山伏や修験者や私度僧などを
ヒジリと表現させていただきます。
漢字の聖ですと
尊い僧侶を意味することもあるので
カタカナでヒジリと
表記させていただき
広義的意味で用いたいと思います。
当地では現在
修験者という言葉が
山伏という言葉と区別なく
用いられている印象がありますが
諸国を遊行する山林修行者のうち
特に祈祷に効験ありとされたものが
修験者と称され
人々に支持されたわけなので
行状の程度等を無視して
用いてしまうと
限定的理解を招きかねないと思うのです。
山林修行の歴史はかなり古いとされ
近年では古代仏教の研究の成果により
かなり重層的なあり方であったことが
解き明かされてきました。
奈良時代になると
日本では山林修行に励む
仏教者が顕著となり
それは大乗仏教的菩薩行の一環として
実践されており
修行者は自利利他の二利を志向した
幅広い活動を行い
それは広く社会に及んでいたとされます。
当山の開創開山は
1200年以上さかのぼる
延暦弘仁年間(782〜824)に
圓鏡上人によるとされ
七崎観音のご出現もまた同等に遡る
天長元年(824)とされ
当地遷座は承和元年(834)とされ
時代区分でいうと平安初期にあたります。
古代仏教についての
先学の膨大な研究成果の力も借りながら
当山の諸縁起について検討することは
有意義であることは言うまでもないですし
当山当地の次代の方々に
竪横な手法のあり方を
示唆することにもつながると思います。
話が専門的になりつつあるので本稿は
語りの一端を担い
その拡散に一役かったのは
ヒジリたちだったとして
結ばせていただきます。