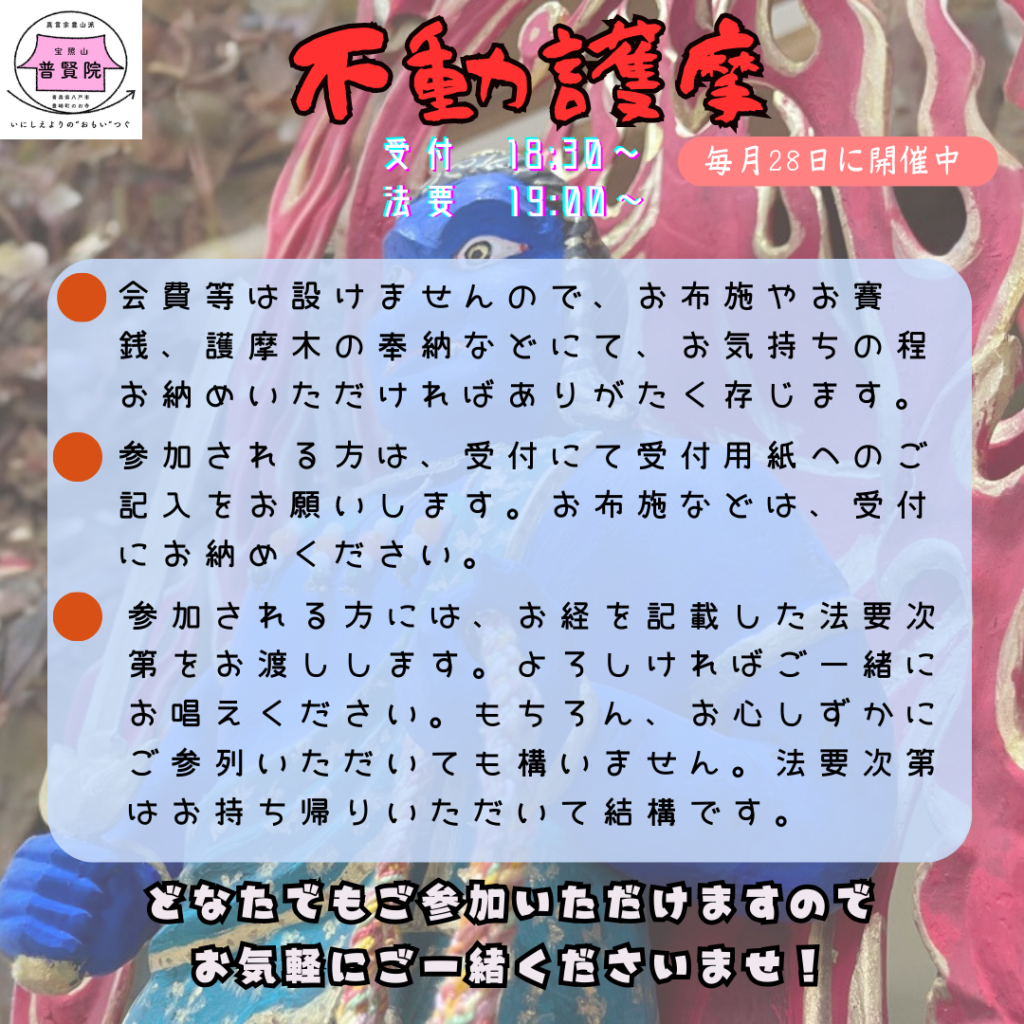位牌堂の位牌合祀スペースに
先代住職と先々代住職の遺筆を
掲額させていただきました。
中央に愛染種字曼荼羅
その左右に金剛界阿字・胎蔵阿字を
設えましたが
これらは先代住職の遺筆です。
両端に宗祖宝号「南無大師遍照金剛」を
設えましたが
これは先々代住職の遺筆です。
なお
このスペースの祭壇も
手直ししていただく予定です。
こちらの合祀所には
位牌堂位牌壇のない方の
位牌を主にお祀りすることを
意図しております。
例えば
諸事情あって
位牌堂に位牌壇を設けることが
難しい場合
個人単位でも位牌を祀ることが出来ますし
合葬墓をご使用の方も
こちらに位牌を祀ることが出来ます。
普賢院の供養法式において
位牌供養は大切なものなので
様々な状況においても
なるべく法式をそろえられるように
合祀スペースの整備に
取り組んでおります。
まだまだ
改善の余地はありますが
多くの方にご安心いただけるような
環境にしたいと思います。
▼Before

▼After